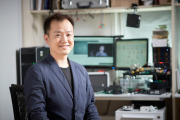「Evangelist」の役割は、可視化されたゴールへ向かう伴走者

映像制作からVR・XR、ドローン、Web開発まで、幅広い技術分野を横断しながら活動する内野清孝さん。「Evangelist」の肩書きで、新たなテクノロジーの可能性を分かりやすく伝える橋渡し役を担っています。海外の現場で得た実体験を武器に、クリエイターたちと共に技術の新たな活用方法を模索し続ける、PERCHを支える人物の一人です。
─PERCHメンバーやベクターデザインと仕事をするようになったきっかけは?
内野:PERCHやベクターデザインを知ったのは、10年以上前にK-relations代表の小林さんの紹介で、このPERCHを訪れたときです。2014年か2015年ごろでした。小林さんとは、それ以前の会社員時代から映像制作の仕事で知り合いだったんです。
転機となったのは数年前で、小林さんがVR系・XR系の仕事を始めたごろです。私もその分野には以前から足を突っ込んでいて、仕事で360°撮影をした経験などもあったので声を掛けてもらい、小林さんと一緒にプロジェクトに取り組むようになりました。当初は小林さん経由での仕事が中心でしたが、PERCHに出入りするうちに梅澤さんと直接話をする機会も増えて、そこから新しい仕事につながることが多くなりました。
梅澤さんの「巻き込み力」の強さはすごいですよね。PERCHに集まる多彩な人材をまとめるのは、実はすごい力なんだと思います。私のような個人で活動している人間にとって、PERCHというコミュニティは貴重な情報交換の場でもあり、新しいプロジェクトが生まれる場でもあります。最近ではAIの活用方法について相談を受けることも増えていて、プロジェクトにおける技術的なアドバイザーとしての役割も担っています。
─内野さんが「Evangelist」を肩書きに選ぶまでに、どんな経緯がありましたか?
内野:実は、この肩書にたどり着くまでには紆余曲折がありました。私の仕事って、説明するのが本当に難しいんです。映像を作ってます、ドローンやってます、360度カメラやってます、VRやりました、Webサイトも作ってます……。説明しても、何をやってる人なのか分からなくなってしまう。
一時期は肩書を完全にやめたこともありました。でも、やっぱり「何をされてる方ですか?」と問われることが多くて。そこで思いついたのが、逆にあまり使われていない言葉にして、それを話のネタにすればいいんじゃないかと。
「Evangelist」という言葉は、昔からずっと頭の中にありました。AppleにGuy Kawasakiという人物がいて、彼の肩書が「Evangelist」でした。広報というか、Appleの技術や、Macで何ができるかを分かりやすく伝える役割を担っていた人で、その響きが面白いなと思っていました。一般的ではない肩書だから「何ですか、それ?」って聞かれることで会話のきっかけにもなります。
CES(Consumer Electronics Show:世界最大級のコンシューマーテクノロジー展示会)で名刺を渡したときの反応が印象的でした。隣に並んでいたアメリカ人と話をしていたんですね。私のつたない英語で自己紹介をしてもよく伝わらなかったんですが、名刺を渡して「Evangelist」の肩書を見た瞬間、「ああ、なるほど」という顔をしてくれたんです。向こうの技術業界にいる人には通じる言葉なんですね。
正直、深い意味があって選んだわけではないんですが(笑)、使ってみると、私がやっていることにピッタリはまるんですよね。いろんな情報を集めて、それをツールとして「こういうのがあるよ」と説明できる立場。企業に属さず、独立した立場から技術の橋渡しをする。それがまさにEvangelistの役割なんだと、後から気づきました。
何より気に入っているのは、この肩書が私を縛らないことです。エンジニアと名乗れば技術が専門だと思われるし、コンサルタントだと助言する人だと思われる。でもEvangelistなら、技術に詳しい人には専門的な話をして、そうでない人にはシンプルに説明する。そういう自由度の高さが、今の私の仕事スタイルにとても合っている気がします。
─最近のお仕事や、手がけているプロジェクトについて教えてください。
内野:最近の仕事は、クリエイターとの協働が中心です。梅澤さんとの仕事もそうですね。AIやVRの技術をある程度理解している人から、一緒にやりませんか?という話が来ることが増えました。そのおかげで、肩書が求められるシーンは減りましたね。肩書は正直なんでもいいから(笑)、一緒に何かをやろうという声を掛けてもらうわけで。
これがとても楽しいんですよね。なんでかな?って考えてみると、クリエイターの方々は明確なゴールを持っているから。「こういうものを作りたい」というビジョンがあって、そのために必要な技術や手法を一緒に探していける。使う側ではなく作る側の視点というところで対等な立場で話ができるのが、その楽しさの源泉なんでしょうね。肩書や何ができるかを問うて来るという、ゴールが見えていないっていうことなのかもしれませんね。
小林さんとの「TaiTock(タイトック)」プロジェクトがまさにそうでした。熟練者の技能をボリュメトリックビデオ(立体映像)で記録して、ベテランの技術をVR映像で初学者に伝授するというゴールは最初から明確でした。当初はVRゴーグルのカメラ1台で撮影した映像を見せる構想だったのが、私がCESで見たソニーの複数カメラシステムの話をしたら、「じゃあそれでやってみよう」となって。2台から4台、最終的に8台のカメラシステムまで発展しました。週に何度か会うたびに新しい機材が増えていて、「また買っちゃいました」っていわれるのが楽しかったですね(笑)。
私が最も避けたいのは「AI使って何かできない?」みたいな、技術ありきのアプローチです。手段が目的になってしまうと、本当に価値のあるものは生みだせません。でも、ゴールが明確なクリエイターとなら、技術の話をしても建設的な議論ができる。お互いが持っている知識や経験を生かし合いながら、新しいものを作っていける。これからも、そういう関係性を大切にしていきたいと思っています。
─これからやりたいこと、挑戦したいことについて教えてください。
内野:来年のCESとSXSW(South by Southwest:毎年3月にテキサス州オースティンで行われる、音楽・映画・インタラクティブなどの大規模イベント)は行きたいです。2023年のCESではヘルステックの出展が急増していて、VRからトレンドが大きくシフトしているのを実感しました。こういう変化は、実際に現地で体験しないと分からない。情報として知っているのと、実際に触れて感じるのとでは全然違います。
例えば、レジ無し無人コンビニ「Amazon GO」で実際に買い物をした様子を動画に撮ったのを、PERCH Schoolで紹介したんですが、現地の方がYouTubeでレポートしているのを見るのとやっぱり違う。日本人の一般ユーザーの感覚を持つ人が、Amazon GOに入ったら便利なのか不便なのか、というところが知りたいんですよね。機能やメリットは伝えやすくても、違和感は伝えづらいですよね。
2018年に深圳に行ったときも同じでした。QRコード決済が普及しているという情報は知っていましたが、実際に露店の野菜売りがQRコードで決済している様子を見たときの衝撃は忘れられません。当時まだPayPayが普及していなかった日本との技術格差を肌で感じました。「QRコード決済?便利なの?Suicaでいいじゃん」と思ってましたから、その意識もガラッと変わりました。こういう実体験を持ち帰って、日本の皆さんに共有することが私の役割の一つだと思っています。
AI技術についても、もっと実用的な活用方法を探っていきたいです。最近VSCodeでJavaScriptを書いていたら、AIが自動でコードを補完してくれて、その精度の高さに驚きました。最初は「余計なことするな」と思っていたんですが(笑)、使い方次第ですごく便利なツールになる。
AIでなくなる仕事もあるけれど、クリエイティブの世界では、むしろAIやプログラムを使うことで新しい仕事は増えるんじゃないですか。仕事が短縮できるから、よりやれることが増えて、新しい仕事をこなせたり。自分が思いもよらなかったことができるようにエンパワーする、というのはかなり強力ですよね。これまで以上に技術やツールを使ううえで「ゴールを明確にする」必要が高まってくるから、これからもEvangelistとして、興味を固定せずに新しい、面白い技術を追っていきたいと思っています。
内野清孝(Evangelist、Creator)
 映像制作からVR・XR、ドローン、Web開発まで、幅広い技術分野を横断しながら活動する内野清孝さん。「Evangelist」の肩書きで、新たなテクノロジーの可能性を分かりやすく伝える橋渡し役を担っています。海外の現場で得た実体験を武器に、クリエイターたちと共に技術の新たな活用方法を模索し続ける、PERCHを支える人物の一人です。
映像制作からVR・XR、ドローン、Web開発まで、幅広い技術分野を横断しながら活動する内野清孝さん。「Evangelist」の肩書きで、新たなテクノロジーの可能性を分かりやすく伝える橋渡し役を担っています。海外の現場で得た実体験を武器に、クリエイターたちと共に技術の新たな活用方法を模索し続ける、PERCHを支える人物の一人です。取材編集/常山 剛
photographs by Tomohide Ikeya.







-180x120.jpg)