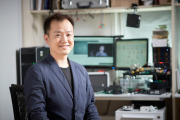フォトアート市場のない時代だからこそ、「フォトアートを売れるギャラリー」になりたい

海外に比べ、日本では市場が確立されていないといわれるアートの世界。文化庁の調査分析リポート「The Japanese Art Market 2024」によれば、日本のアート市場の市場規模(2023年の総売上高)は6億8,100万ドルで世界のアート市場の約1%に過ぎません。昨年からPERCHのメンバーに加わり、日本でのフォトアート市場の創出を目指しているのがフォトアート専門ギャラリー「tokyoarts gallery(東京アーツギャラリー)」の古村健一さんです。
コロナ禍を機に「ギャラリーは場所ではなく企画力」という発想へ転換。写真家とタレントのコラボレーション企画や移動型の展示会を手がけながら、「複製可能な写真がなぜ高額なのか」という買い手の疑問に向き合い、アーティストと二人三脚でフォトアートの価値を伝える取り組みを続けています。その古村さんがPERCHへ入居した経緯は、写真家の池谷さんとの出会いがきっかけでした。
ギャラリービジネスの始まりと変遷
ー古村さんはこれまでにも、アートと関わりのあるお仕事をされていたのですか?
古村:いえ、まったく畑違いです。元々は投資用不動産の営業で、その後はファンド会社に転職してまた営業をしていました。その当時の顧客だったファンドのオーナーさん、それに知り合いの写真家の方から「フォトアートってこれから売れるよ」とか「まだ市場が形成されていないジャンルだから今後おもしろくなる」という話を同時期に聞いていたんです。それで「写真専門のギャラリー」というアイデアが立ち上がり、また別のファンドオーナーで写真好きな方が、その構想をおもしろがって投資してくれたのが東京アーツギャラリーの始まりでした。
私はまだファンド会社の社員だったから、他の社員をスタッフとして手配するなど、外部の立場からギャラリー立ち上げのサポートをする程度でしたね。まだギャラリーもアート写真も、まったく分かってなかったころです。東京アーツに入社したのも、それから2年弱ほど後のことでした。
ーそうなんですね、てっきりカメラマンだったり、アーティストだったのかと。池谷さんとお知り合いになったのも、そのころですか?
古村:2012年にギャラリーができてから何年かあと、池谷さんの個展を私たちのギャラリーで開催してもらったのが最初の接点です。「古村君のところっておもしろいよね、ギャラリーっぽくなくて」といわれたことがありました。作品を売らなきゃギャラリーのビジネスは成り立たないから、売ろうとはしているけど、ギャラリーに入っていきなり、売らんかなって顔を隠しながら作品の話をされてもお客さんには分かっちゃうし、きっと嫌じゃないですか。
普通のギャラリーなら来場者があれば「今展示している作品はこうです、この作家はこうです」といった話から始まりますが、うちは違いました。「暑いですね、大丈夫でした?」「今日は雨が降りそうですね」みたいな世間話から入る。そんな自然体のコミュニケーションを、池谷さんはおもしろがってくれたみたいです。
当時の東京アーツギャラリーは渋谷区東の、明治通り沿いの路面物件で、何をするにも便利な立地でした。車で来ても停めて入れるし、ギャラリースペースとしても個展をするぐらいなら広すぎず狭すぎず、天井高も3m50cmぐらいあって。そこで8年ぐらいやっていておもしろかったんですけど。

ー2012年から8年後ということは、コロナ禍ですね。
古村:そう、コロナで大ダメージです。家賃だけがかかって、展示はできないし人も呼べない。そのときのダメージが結構大きくて、渋谷から麻布十番にギャラリーを移転したんですが、そこも2年ぐらいですぐ閉めました。でも、決まっていた展示や案件もあって、会社としてギャラリーはずっとやっていくつもりでした。また新しく移転して、ギャラリーを持つかどうかと考えたときに、しばらくは自前の展示場所を持たず、移動ギャラリーのような形で展示場所を借りて企画する方向に切り替えました。とはいえ、オフィスや倉庫、法人登記の住所も必要だということで、物件を探しました。不動産業界時代の人脈を使っても、なかなかいい物件が出ない。どこでもいいかと諦めていたときに池谷さんと話をする機会があって、「PERCHが空いてるよ」と教えてくれたんです。
ーPERCHの第一印象は?
古村:池谷さんと仕事をしたときに出入りしていたので、PERCHのことは知っていました。ロフトがあったり、小屋があったり、変わった場所だなって(笑)。ベクターデザインとも、コロナ禍にネット配信をするときに、Wi-Fiルーターとかを調達させてもらったりっていう関係性があったんです。PERCHなら賃貸オフィスよりもイニシャルコストが抑えられて、住所も持てるから、取りあえずのオフィスとしては十分だと思って入りました。
アートビジネスの難しさと課題

ーアートビジネスの難しさは種々あると思いますが、その要因はどこにあるのでしょうか?
古村:ビジネスとしてアートを扱って10年以上になりますけど……現在は「もうけ話としてやるものではない」という結論に至ってます(笑)。
要因を挙げるなら、フォトアートの市場が日本では成立していない点です。絵画なら一般の人でも、購入しようと思えば数多ある画廊に行けばいいし、値段の相場もあります。フォトアート作品を扱っている場所も少ないし、そもそも著名なアートフォトグラファーがまずいない。日本人の写真家で、写真アーティストと聞いて思い浮かべる大物写真家のほとんどは、商業カメラマンです。今、世界で有名な日本のフォトアート写真家といったら、森山大道か杉本博司か、せいぜい5本の指で数えられるくらい。それこそ、この前亡くなった篠山紀信さんも日本では有名な写真家ですが、世界で見れば知られていないし、作品に値がつくかといったら、つかないです。
そもそもフォトアートの歴史がまだ短いという点も関わっていると思います。現在の写真技術が発明されたのが約100年前、フォトアートの歴史はもっと短いです。1000年以上あるアートの長い歴史から見れば、ほんのわずかにすぎません。
ーマーケティングがどうこう以前の、土壌作りからですね。
古村:アート全般に対する文化的土壌という課題もあるでしょう。写真に限らず、アートを飾っておける壁がある家は日本では少ないですし、ホームパーティーで家に人を呼ぶ文化もないです。海外だと家の壁にアートを飾って、客人にそれを見せたり、アートをきっかけに会話をしたりするのが当たり前、というところもあります。
また写真の売り方、値付けの問題もありますね。写真は複製できるから、エディションをつけて限定販売します。ところが、写真家側も売り方も分かっていなくて、大御所の写真家でも、曖昧な高すぎる値付けをしてしまうことが多かったんです。今、フォトアートの市場をちゃんと成立させようとしている写真家やギャラリーは、そのよくない前例と戦っているようなものですね。
とはいえ、すでに確立されている市場でビジネスをやってもおもしろみがない。一方、まだ市場が開発されていないフォトアートだからこそ、「フォトアートを売れるギャラリー」の嚆矢になれたらおもしろいというのが、この仕事を続ける原動力ですね。
ーギャラリーの役割とアーティストとの関係性はどう考えていますか?
古村:写真に限らず、アートの世界は技術が高いのは当たり前で、コンセプトの独自性やそのコンセプトを作品や文章を通じて伝えることが、作品成立の大きなウエートを占めます。誰もやったことがないもの、作り上げていないものへのチャレンジという点では、フォトアート市場を作るのと似ています。ギャラリーは新しいものを作り出せませんから、それに対して一生懸命もがいて、頑張っている池谷さんのような写真家をギャラリーとして応援したいんです。
ギャラリーは、人の作品で商売をさせてもらっていることも忘れないようにしながら「写真を売るプロ」というスタンスを保ちたいとも考えています。アーティスト自身が売ることまで考えてしまうと、作るものは変わってしまう。売れる作品ばかり作っちゃいますからね。「古村君のところに作品を持っていったら何でも売ってくれる」なら、このPERCHの小さな会議室でも、どこでやっていてもいいんです。それはギャラリーを持たない選択をした理由にもなっています。
ー具体的には、どのような取り組みをされていますか?
古村:東京アーツギャラリーでよく手がけているのは、写真家とタレントとのコラボ作品の展示です。意識しているのは、モデルが写真家にリスペクトできる関係性を作ること。作品にも感じられますし、タレントのファンがギャラリーに来場するきっかけも増えます。フォトアートと縁がなかったファンの方が、フォトアートに接してもらうことで、写真家のファンにもなってくれる。すると、写真家が別の展示をやったりそれを見に来てくれるという、循環を生み出したいと考えています。
コラボ作品展示では、展示会で写真家が撮影する作品を購入いただくと、タレントと購入者のツーショットを作品として撮影できる来場者特典を提供していますが、「ツーショット撮影するのに5万円出さなきゃならないの?」といわれることもあります。あくまでも作品の価値が5万円であって、ツーショットは特典だと説明するんですが。
ー撮影という役務ではなく、作品の価値への対価ということですよね。
古村:写真がデジカメやスマホで誰でも撮れるようになって、フォトアートの値段が成立しづらい時代になりました。でも、この10数年で変わってきているとは感じます。池谷さんの水中写真の作品を見れば「こんな写真は池谷さん以外には撮れない」と分かりますからね。
池谷さんに「もっと、他のものも撮ってみたら?」といったら「まだまだ売れていないんだよ。今も、もがきながら一生懸命やっているんだ」と返されました。僕らは池谷さんのすごさもよく知っていますが、まだ足りないと本人は思っている。だから次のことをやるより、まず知られるようになるためにやるべきことは多いと気づかされました。
ものも、情報も、人手も、コミュニケーションも融通しやすい場所
ーPERCHメンバーや、場所に対する印象を教えてください。
古村:ここではいろいろなジャンルの特技を持っている人たちと、何かあったときに共有できるし、情報交換もできますね。展示に使う材料や道具一つにしても「こんな照明が欲しい」といえば「あるよ」って出てくるんですよね。池谷さんとは以前から仕事してますけど、今ではすぐ横ですから、納品されたデータに気になるところがあれば池谷さんにお願いして見てもらったり。池谷さんのアシスタントさんにイベントに使う荷物の発送作業や仕分けを手伝ってもらったり。その逆に、池谷さんが展示するときにスタッフが足りないと聞いたら、無償で手伝ったり、そういう関係性ができています。私みたいに、それをいいと思う人にとっては居心地がいい場所だと思います。
ー古村さんにも、PERCHの水が合ってたんですね。
古村:普通のシェアオフィスって間仕切りがあって、お隣同士でもあんまり関わりがないというイメージでしたが、PERCHは逆ですね。僕はいろんな人と関わるほうが好きだったんで、PERCHみたいなオープンな場のほうがやりやすいし、そういう感覚を共有できている場所だと思っています。あと、僕らが過ごしやすくするためにベクターデザインがこの場を作っているわけではなく、梅澤さんたちが居心地のいい空間を作って、そこにみんなが来てよろこんでくれている感じ。例えば、あのダクトを見てください。

ーエアコンの先から奥の部屋へと伸びてる、あれですね。
古村:奥側に空調がないので、あちらの席は暑かったんです。それを梅澤さんがなんとかしようって作ってくれました。単に通気用のダクトだけ造作するのかと思ったら、エアコンの冷風を強制的に吸い込んで奥に送る送風ファンも一緒に、梅澤さんたちが自分で作ったんですよ。そういうのを自分たちで作るというのがおもしろいですよね。一時的な仮住まいのつもりだったのですが、居心地がよいから2年弱くらいいます。
ーPERCHに求めるものや、もっと欲しいものはありますか?
古村:うちの会社だけのニーズだけど、倉庫かな…。藤﨑さんの「小屋」くらいの広さの。今は西荻窪に額装や展示品を保管する倉庫を借りていて、PERCHの近くにあればとは思いますが、さすがに代々木だと家賃が安くはないので。梅澤さんに相談したら、「PERCHの入ってるミサワビルの反対側がマンションなんだけど、そこのワンルームが空くかも?」という話を教えてくれて。期待して待ってます。
そうですね、シャワーがあれば完璧ですね。飲んで遅くなっても、代々木なら新宿からも恵比寿からもタクシーですぐ。実は、すでにここに着替えが2〜3着あるんですよ。ドリンクバーも充実してるし、シャワーがあったら何もいうことないです。でもあったらあったで家に帰らなくなるから、逆にないほうが正解なんでしょうね(笑)。
tokyoartsgallery
 新進気鋭の作家と共にオリジナル展覧会を企画発表しています。 国際的なアートフェアにも出展し、日本の現代アートを世界へ発信しています。 タレント(俳優、女優、ミュージシャン、声優、アスリート・・・)を、モデルとしアート作品を作り込みます。
新進気鋭の作家と共にオリジナル展覧会を企画発表しています。 国際的なアートフェアにも出展し、日本の現代アートを世界へ発信しています。 タレント(俳優、女優、ミュージシャン、声優、アスリート・・・)を、モデルとしアート作品を作り込みます。ギャラリーとしての品位を保ち、“変化し心動かされる”そんな空間を演出し作品づくりに力を注ぎます。
取材編集/常山 剛
photographs by Tomohide Ikeya.







-180x120.jpg)