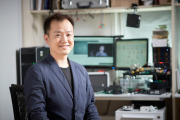AI時代にこそ求められる「ジェネラリスト系エンジニア」

─ベクターデザインの取締役に就任するまでの経歴は?
松原:新卒で入社した東芝の子会社では、エンジニアとしてガラケーに搭載するソフトウエアの開発や、他社のカーナビやポータブルゲーム端末に供給する車載用ポータブルナビゲーションシステムの開発を担当していました。ガラケーの最盛期で、仕事場は携帯の工場でしたね。そこで10年ほど勤めたあと、これまでとは異なる環境を求めて、東大生・東工大生の立ち上げたジョイントベンチャーの設立に加わりました。今のAIや機械学習の前身になる技術を活用してSNS投稿の自動でフィルタリングするシステムを開発し、事業化を行いました。
その後も30歳〜40歳代はスタートアップでの経験を積み続け、株式会社ユーザベースではNewsPicksのAndroidアプリのエンジニアとしてプレイングマネージャーを担当しました。現在も、ベクターデザインの取締役を務めながら、数社のスタートアップでエンジニアとしての業務を続けています。
エンジニアリングやプログラミングは濃淡はありこそすれ、20年〜30年くらいは続けています。なぜそんなに続けていられるかと言われる、あまり考えたことはないんですが……。「何が何でも長生きしたい!」という気持ちの薄い、生には執着がないほうだとは思いますが、「あの新しい技術が見られないうちに死ぬのは、ちょっとイヤだ」とは思うんですよね。なるべくなら長生きして、どんな感じになるのか見てみたい。リニア新幹線とかもそうですね。クルマも近々宙を浮くかもしれませんし。そういった新しいものへの興味がなくなった自分がいたら、エンジニアとしても良くない傾向だなと思います。だからこそ、なるべく好き嫌いをせずに新しいことも、取りあえずモグモグしてみる姿勢が原動力なのかなと思っています。
─ベクターデザインとの最初の接点は?
松原:梅澤と初めて会ったのは10〜15年くらい前、Twitterで呼びかけされたエンジニアのお花見の席です。当時はベンチャーにいて、半ば会社に泊まっているような生活だったので、花見の差し入れに選んだのがコンビニで売っていたレッドブルの6缶ケース。それが梅澤の印象に残ったらしく(笑)、徐々につきあいが増えていって、仕事でもつながるようになりました。
梅澤の印象は「巻き込み力がある人」。さまざまなジャンルの人を巻き込んで、新しいプロジェクトを推進する力に長けているタイプですよね。PERCHに集うような、まさに多彩で多才な人たちを一つにまとめる中心的存在だと思います。梅澤やPERCHのメンバーは大企業のエンジニアだったときには直接話をするきっかけがなかった人たちでしょう。そもそも東芝グループで担当していたのは、オープンにできない組み込み系のシステムで、ほかのエンジニアと情報交換や改善相談ができる環境ではなかったので、ベンチャーへ転職してからWeb系のエンジニアが集まる勉強会を経験したときは新鮮でした。
─エンジニアとしての立ち位置は?
松原:エンジニアを「特定の領域を突き詰める“職人”タイプ」と「広い分野を一通り理解している“ジェネラリスト”タイプ」の2タイプに分けるとすれば、自分は後者です。10年サイクルで技術が刷新されるIT業界では、専門性を追求するだけでは将来的なリスクがあります。それこそ、AIが進歩すればこれまでの技術はAIが代わりにやってくれる可能性も高くなります。自分のできることを多面的に増やして、時代の変化に対するヘッジを図っています。
それぞれの分野の専門家ほどではありませんが、仕事ができる程度には知っているという立場から、デザイナーや編集、営業といった、エンジニア以外の職種とコラボレーションを通じて、エンジニアが動きやすい環境を構築する役割を担うことが多いです。エンジニアと非エンジニアとのコミュニケーションギャップを埋める役割は、今後いっそう重要になってくるでしょう。役割という意味では「0から0.1を生み出す」のではなく「0.1を2にする」ことで、その役割を全うしたあとは「2を100にするタイプ」へとバトンをパスする役回りが多いです。
─ベクターデザインでの役割は?
松原:ベクターデザインでの役割は、特定のプロジェクトの専属ではなく、軽いフットワークで動く「こぼれたボールを拾う役」ですね。ベクターデザインではインフラを含めて自社開発するケースも多く、業務で直接サーバーラックを触ることも増えました。今までの仕事でWebインフラに関わることはあっても、業務としてサーバーラックに直接触れる機会は少なかったので知識の幅が広がりました。その一つが、ベクターデザインが提供している行政機関向けの気象観測・防災IoTシステムサービスです。エンジニアとしての技術的な関わりのほか、行政特有の予算執行方法やリクエストに対応する経験は、私のエンジニアとしての手札を増やすものになりました。東芝グループ全体では対行政の仕事もありましたが、私の部署とは縁がない相手だったので新鮮でしたね。
─ベクターデザインが抱える課題は?
松原:自分たちのできること・やってきたことをもっと外部に発信するのが重要ですし、課題だと感じています。例えば、ベクターデザインが手がけているクラウド防災IoTシステムなどは、最先端の技術ではないものの、一歩間違えれば人の命に関わる領域の非常に重要なサービスです。気象データや水位データを大量に扱える業種や仕事は案外限られているし、技術的領域にも非常にニッチでおもしろいことをやっているんですよね。PERCHメンバーは発信そのものが仕事でもあるから、ベクターデザインという会社での発信方法は違ってくるとは思いますが、PERCHメンバーのように技術力や領域自体のおもしろさをもっと伝えられたらと思っています。
─エンジニアリングの今後の展望は?
松原:生成AIの進歩は非常に早く、すでに初学者のエンジニアができることは、AIでほぼ代替できる状況になっています。Newsweekの報道によると、アメリカではコンピューターサイエンスを専攻した学生の「失業率」が6.7%で、ワースト7位だったという話もあります。AIの能力とは違う付加価値を出そうとすると、AIの出力する内容を分かっていないとなりません。ところが、勉強していないとAIによる成果を判断できないのに、初学者よりもAIのほうがいいものを書いてしまうから、勉強する機会をAIに奪われてしまいかねません。私たちの世代の若いときと比べて、今の若い人は大変だと思います。
その代わり、勉強手段としてAIを使うのはアリですよね。何度同じことを聞いても怒り出すこともないですから。AIに対する見え方も僕らの世代とは変わってくるんだと思います。また、AIに書かせて、自分はレビュアーになるスタイルが主軸になると、エンジニアに求められるクオリティの種類や仕事のやり方も変わってくるのではないでしょうか。EQ(情動知能指数)であるとか、相手が何を求めているのかを正しくくみ取る能力のほうが、エンジニアにとって重要になってくるかもしれません。
─一緒に仕事をしたい人物像は?
松原:技術的な何かに興味を持って、その興味を持ったことに対してフィードバックをくれる人と仕事をしたいです。例えば、作業をお願いする仕事のやりとりだけだと、ちょっと寂しいから、技術的な情報の交流が双方向でできる人だとうれしいですね。個人的に興味が強いのは、やっぱりAI技術の話ですね。AIの進歩に対する焦りを感じると同時に仕事では避けて通れない面もあるので、折り合いの付け方などをお互いに情報交換できたら、会社全体にもフィードバックできるのではないかと考えています。あとは、職人としてのエンジニアに対して思っていることを誤解なく伝えたり、こちらの要望を踏まえて手を動かしもらうコツなども伝えられたらいいですね。
松原孝司(ベクターデザイン取締役)
 PERCHの運営企業、株式会社ベクターデザインの取締役。総合電機メーカー子会社でソフトウエア開発を担当。その後はベンチャーやスタートアップ企業でAndroidアプリ、Webシステムの開発を担当。2023年より取締役に就任。
PERCHの運営企業、株式会社ベクターデザインの取締役。総合電機メーカー子会社でソフトウエア開発を担当。その後はベンチャーやスタートアップ企業でAndroidアプリ、Webシステムの開発を担当。2023年より取締役に就任。取材編集/常山 剛
photographs by Tomohide Ikeya.








-180x120.jpg)